経済記者として40年間、市場経済を見続けてきたという永野健二氏は、自らの著書について「バブルの時代を知らない若い人たちに読んでほしい」と親しい知人に語っていたという。
私は永野氏と同年齢であり、ほぼ同じ期間を新聞記者として過ごしてきた。ただし、取材対象は異なり、市場経済に関しては、基礎的にも、実践的にも、まったく知識がない。
したがって、若い人たちではなく、バブルの時代を知らない人でも実はないのだが、本書を読んで、「バブル」についてはあまりにも知らないことばかりだったなあ、と改めて認識するに至った。
もう少し別の言い方をすれば、自分がバブルの時代と思っていたものが、本書にはずいぶんと異なる姿で示されており、しかも、次々に登場する人物のエピソードや評価を通して、その姿が説得力をもって伝わってくる。思いもかけず、そんな貴重な読書体験に遭遇した。長生きはするものである。
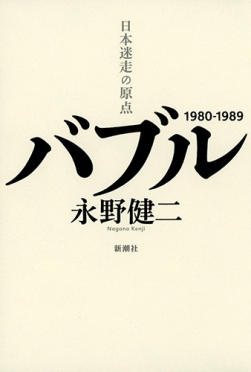
本書は第1章 胎動 から 第4章 精算 まで、ほぼ時代の推移に沿ってバブル前史からバブル崩壊後の失われた20年に至る過程が報告されている。第1章では、80年代前半までの戦後経済の流れが紹介され、永野氏はその中でいくつかの「事件」を取り上げつつバブルを招くに至った構造的要因を概括している。第2章 膨張は1985年のプラザ合意を起点としたバブルの拡大期。第3章 狂乱は88~89年の《お金だけが尺度となり、裏と表の世界が渾然一体となった異常な時代》を描く。そして、第4章はバブル崩壊後の精算(の失敗)と失意の日々であり、失われた20年を招くに至った経緯についても永野氏の視点から言及している。
その本編に先立つ「はじめに」の数ページの中で、著者は2つバブルの定義を示している。一つは「バブル経済について」。
《特定の資産価値(株式や不動産)が実体から掛け離れて上昇することで、持続的な市場経済の運営が不可能になってしまう現象のことである》
そしてもう一つは直裁に「バブルとは」。
《グローバル化による世界システムの一体化のうねりに対して、それぞれの国や地域が固有の文化や制度、人間の価値観を維持しようとしたときに生じる矛盾と乖離であり、それが生み出す物語である》
どちらも明確で、分かりやすい・・・と少なくとも私は思った。そして以下4章では、その後者の定義が生み出す人間の物語を中心に魅力的でかつ痛切な教訓にも満ちた報告が続けられる。
個人的な興味に引きつけた感想で恐縮だが、敗戦からの復興と高度成長を実現した戦後システムの崩壊を指摘するところから本文の記述が始まっていることにまず注目したい。その崩壊が変革につながらず、戦後システムの延命を画策する過程こそが、バブルの担い手達の登場を促す要因でもあった。
時間軸を大きくとり、個別のエピソードを戦後経済史の流れの中に位置づけていく手際の鮮やかさは、全編を通して見事である。おそらくは書き手の長い取材体験に基づくリアリティが、個々の凝縮された記述に力を与えているからだろう。
そこに本書の第一の魅力がある。単なるビジネス書でも、暴露本でもない。バブルを知らない若い世代に読んでほしいと、うかつにもバブルを(あまりよく)知らなかった高齢層の一人としても思う。
もう一つの大きな魅力は、バブル戦国史とも言うべき躍動感だろう。様々な人物の暗躍や策謀、理想、抱負、挫折、落剥、そして、それと隣り合わせの裏切りや保身といったものが次々に描かれていく。先ほどの繰り返しになるが、個々の記述は比較的、淡々とした印象を受ける。良質の素材に対する自信だろうか。一部社会部記者に見られる味付けの濃さやくどさはあまりない。
それでもさまざまなシーンが見事に浮かび上がってくるのはどうしてだろう。本書にある種の求心力を与え、本文記述に躍動性を与えている秘密は、各章冒頭の1ページに掲げられている時代背景の要約にあるのではないかと個人的には思う。
章が改まるごとに、私はNHK大河ドラマ『真田丸』冒頭の有働アナウンサーによるナレーションを聞くようにしてこの要約を読んだ。そこで一応の俯瞰図を得たうえで、栄枯盛衰、諸行無常の物語に入っていく。その対照の妙は心憎い。何かまとまったものを書く機会があれば、この手口はちょっと拝借してみたいとも思う。
話が少々脱線した。バブルの物語は本書を読んで十分、堪能していただくとして、「おわりに」と題した文章にも少し触れておきたい。
《誰が何にチャレンジしていたのか。そして何に敗れ、何に否定されたのか。バブルの時代という大きなうねりのなかで敗れていった人たちや、否定された人たちの行動の中にこそ、変革の正しい道筋があったのではないか》
本書に紹介された多数のバブル紳士たちのほとんどは(というよりも全員が)私の知らない人たちであり、私には著者の指摘にただちに同意できる材料は何も持ち合わせていない。ただし、そうかもしれないとも思う。
「おわりに」に示された苦い述懐の中には、良質のミステリーの謎解き編を読むかのように「ああ、そうなのか」と腑に落ちる記述がたくさんあり、著者が何に怒りを感じているのかも、比較的、真っ直ぐに伝わってくる。
《われわれは生きている時代に真摯に向き合わなければならない。だからこそ、日本のバブルを今一度学び直す必要があると思う》
40年間、市場経済を見続けてきた経済記者があえて韜晦を排し、こう書く。日本という国の現状に対する強い危機感が込められていることは、ほぼ同時代をうかつなままに過ごしてきてしまった同年齢の記者にも容易に伝わってくる。考えて見れば、これは、この本にとっては素晴らしく、日本の現状にとっては少し残念なことでもある。
他の人も書いていたが、「あとがき」には、思わずほろっとしたことも付け加えておこう。